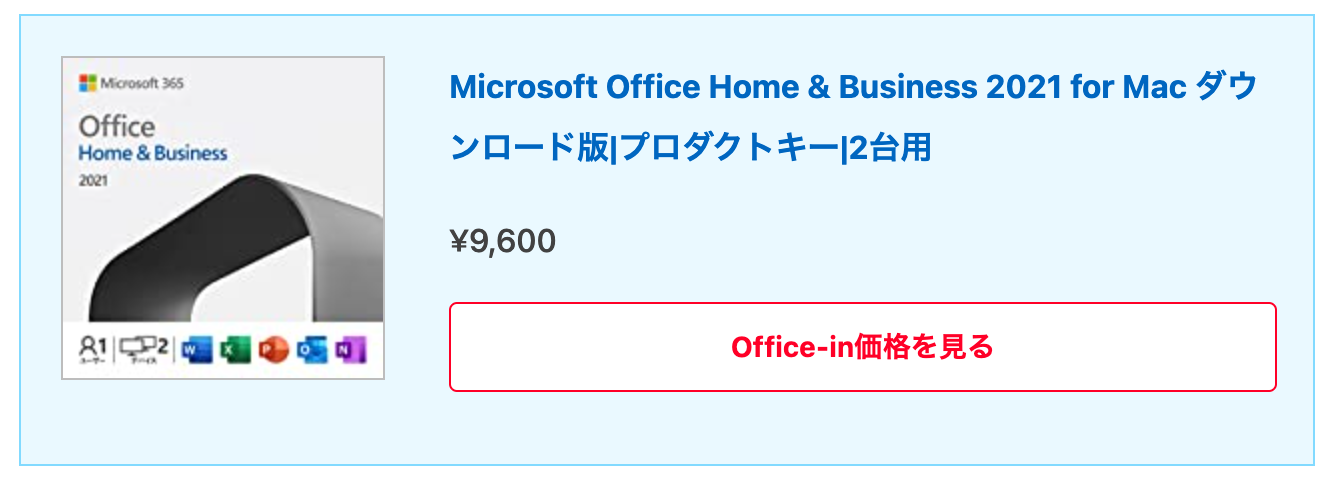埼玉県鴻巣市では2021年4月、市内の全27の小中学校の児童・生徒に、一人一台のPC環境を整備すると同時に、システムをフルクラウド化し、学校内のみならず、自宅でもICTを活用しながら学習できる環境を整えた。目的はICTを文房具のように活用できる環境の提供だという。

鴻巣市市役所
また同時に、統合型校務支援システムを刷新し、先生の負担を軽減、在校等時間の削減を図っている
なぜ、クラウドを採用したのか?
同市では、それまで利用していた学校内のICT環境が2020年に更新時期を迎えるため、2018年から、今後、どういったICT環境を整備すべきか検討を始めたという。
そこで、2019年9月に「鴻巣市学校教育情報化推進計画」を策定し、GIGAスクール構想が本格化する前から、一人一台の環境整備に動き出した。
鴻巣市学校教育情報化推進計画の中では、鴻巣市の課題として、「教材研究や準備・校務においてのICTの活用は図られているものの、日常的に授業で使用できるようなICT機器の整備が十分でないことに起因し、教材や授業で効果的なICT機器の活用ができていない」という点を挙げている。
そして、整備の基本方針として、「授業や校務において日常的にICT機器が活用できる環境を整備する」、「教育現場において先端技術を活用することで、新しい時代で活躍するための基盤となる力の習得と教育の質の向上を目指す」の2点を定めている。これには、鴻巣市の原口和久市長の教育ICT推進への想いが強かったことも大きく影響した。

鴻巣市教育部教育総務課 主任 新井亮裕氏
鴻巣市 教育部 教育総務課 主任 新井亮裕氏は、「重要視したのは、先端技術を活用したネットワークやクラウドアプリケーションなどインフラの整備です。ICTは社会や企業で拡がってきており、学校現場だけが追い付いていない印象を受けました。子どもたちがいつでもどこでも学ぶことが出来る環境と、先生達もこれまで職場に行かなければできなかった業務を自由にどこでもできるように、セキュリティの高い教育ICT基盤を整備することが重要だと感じました。教育情報化推進計画は、ICT機器を活用し、新しい時代で活躍するための資質能力を身に付けるという基本理念を定めておりますが、キーワードとしては、“ICTを文房具のように使って欲しい”という考えがありました。ICT機器を授業で使うことが目的ではないですし、ICTばかりが主役となる授業を求めるものではありません。紙と鉛筆のように子どもたちが自然にICT機器を使う姿を目指しています」と語る。
学校教育情報化推進計画に基づいた整備では、校務事務を電子化する、先生は一台のPCを授業、校務、自宅で利用する、システムはクラウド化し、いつでもどこでもアクセスできる環境にする、セキュリティはゼロトラストの考え方を採用するというものだ。
クラウド環境は、鴻巣市独自の閉域網と学術情報ネットワーク(SINET)を介してMicrosoft Azureに接続、Microsoft 365 Educationを活用している。SINETは、全国の大学、研究機関等の学術情報基盤として、国立情報学研究所(NII)が構築、運用している情報通信ネットワークで、これを利用することにより、強固なセキュリティ基盤を構築した。国内の教育委員会で初めて接続した最先端のICT環境だ。

鴻巣市が整備した教育ICT環境
フルクラウド化に関して新井氏は、「先生達が学校、教室、自宅のどこでも使える環境となると、フルクラウドということになりました。オンプレミスの場合は、専用のセキュリティソリューションを別途導入する必要があり、ユーザビリティやコストの面からハードルが高かったです。クラウドにしてゼロトラストの考え方を取り入れればセキュリティリスクに対しても安心できます。また、クラウド化することにより地理冗長化までを含めて簡単に実現できるというメリットがあります」と、採用の理由を説明する。
パソコンはキーボード付を選択
児童・生徒用に導入したPCは、デルのLatitude 3190 2-in-1。キーボード付でタブレットとしても利用できる。
小学校では、キーボードなしのタブレットを採用するケースが多いが、同市では文字入力させることを想定し、キーボード付のPCを選択したという。なお、パソコンは小1で提供されたものを、小6まで使うことにしている。

鴻巣市立鴻巣中央小学校でのPCを活用した授業風景(3年生)
各教室には、無線LANと電子黒板を導入。児童の画面を共有しながら発表が行えるようになっている。

児童の資料を投影する電子黒板。発言する児童の注目してもらいたい点を先生が拡大表示している

授業中の先生のPC画面。各児童の状況が確認できる。なお、先生のPCはSurface Pro 7を採用した
-

PCを使わないときは教室内のカゴで保管
-

自宅に持ち帰らないときには、PCをキャビネットに格納して帰宅する。充電が可能なため、PC付属の電源コードは自宅に置いておく。そのため、通学で電源コードを持ち運ぶ必要がない
児童や教員が使用するPCには、学校向け学習eポータル「L-Gate(エルゲート)」を導入している。PCの起動と同時に立ち上がり、授業で使う教材やアプリに素早くアクセスできる。ユーザーや学校クラスの管理機能、アクセスログを蓄積する機能を活用し、PCの利用状況を見える化できるようにしている。

内田洋行の「L-Gate」のインターフェース画面。トップページには、学校の先生や教育委員会からの「お知らせ」が表示される。その他、授業で使用するWebアプリを登録できる「教材・アプリ」や、「アンケート」「利用履歴」機能などを備え、日々の学びをサポートする
また、内田洋行の教育コンテンツクラウド配信サービス「EduMall(エデュモール)」やオンラインドリル等も活用できるほか、ベネッセの協働学習支援アプリ「ミライシード」も利用しており、すべてL-Gateからアクセスできるようになっている。

鴻巣市立鴻巣中央小学校 清水励氏
パソコン導入の効果について、鴻巣市立鴻巣中央小学校 校長 清水励氏は、「子どもたちは進んで文章を書く子は多くありませんが、PCを使うと文字の上限を超えるくらい、感想などを書いてきてくれます。文字を書くという壁がすごく大きかったのだと改めて感じます。」と述べる。
導入後の児童間のICTスキル格差ついて清水校長は、「どのクラスにも先陣を切る『ミニ先生』のような児童がいるので、その子をお手本にすることで、自然と伝播していきます。逆に先生が聞くこともあるくらい、子どもたちが進化しています。」と語った。
コロナ禍では、在宅でのWebを使った双方向の授業は行わなかったそうだが、最初の休校時はWebを使った情報発信は積極的に行ったという。
「一斉休校が卒業式間近だったため、急遽オンライン対応を行う事にしました。学校からのメッセージ動画を発信したり、卒業式の練習動画をつくって、子ども達が家で自主練できるようにしたりしましたが、卒業式当日は、子供たちは立派に証書受け取りが行え、問題なく式を挙行できました。先生方も、動画配信の有効性と可能性に気付き始め、その後も続いた休校時には、約90本の学習用動画を作成・配信し、子供たちと学校とのつながりを大切にした取組みを行ってきました」(清水氏)
PCの授業での活用方法については、基本、各先生に任されているという。
「先生には、失敗してもいいからやってみようと言っています。その上で、アナログとデジタルで良い部分を使い分けるようにする。児童にどういった力を付けさせたいのかによって、授業のやり方が変わってくると思います」(清水氏)